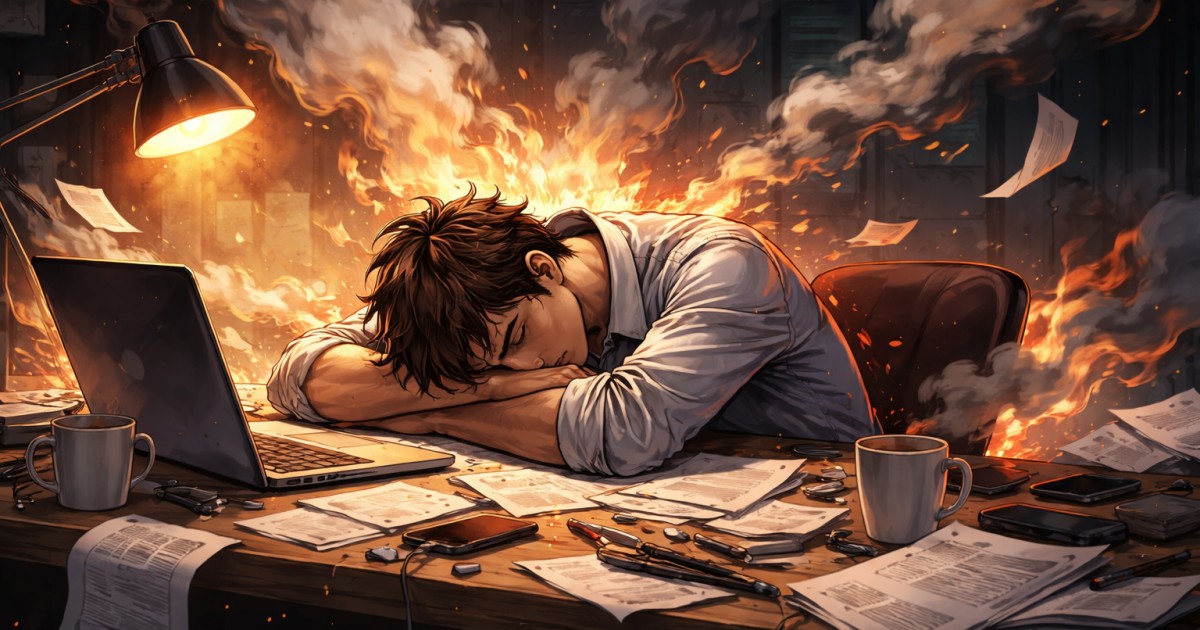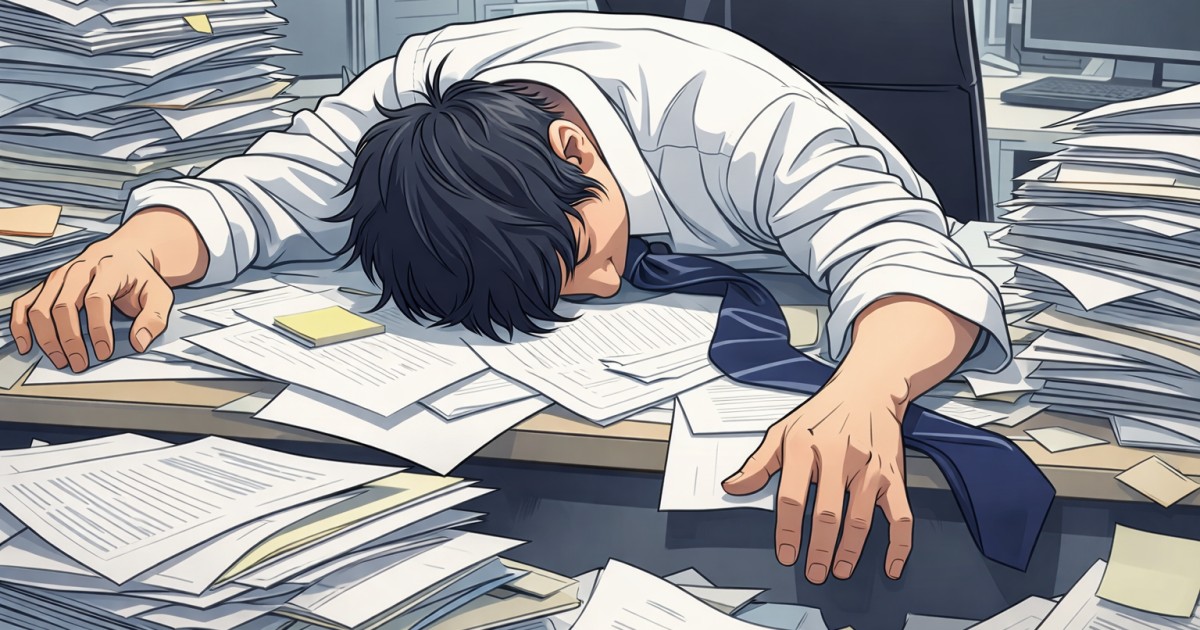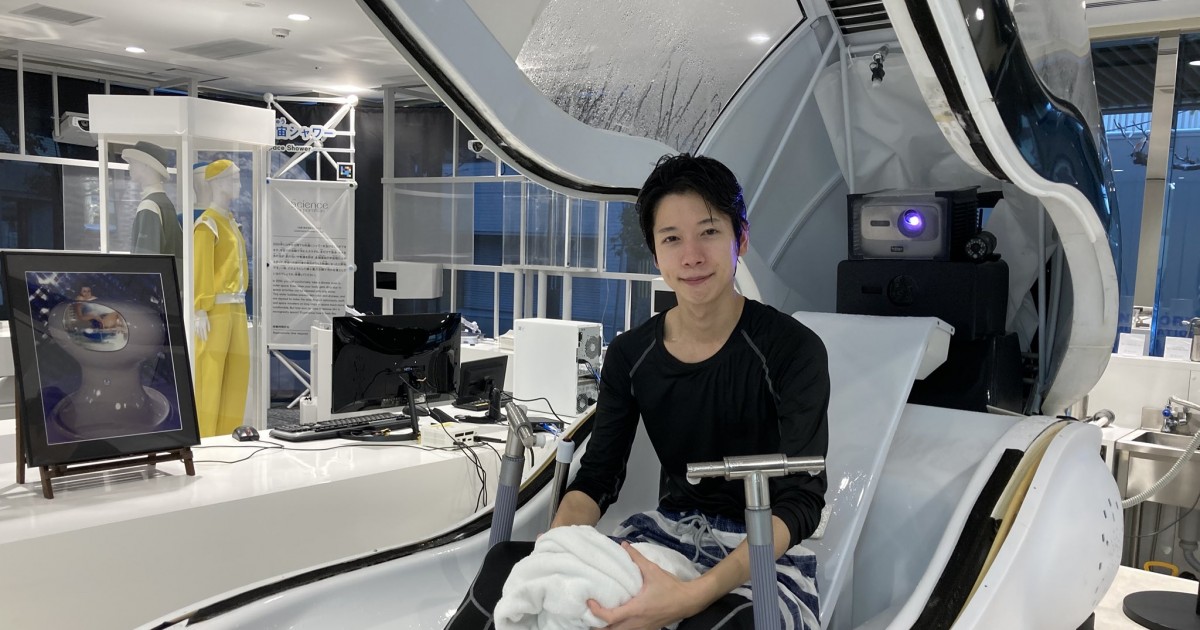発達障害?アスペルガー?自閉スペクトラム症の特徴8つを精神科医が丸わかり解説
いきます。
「アスペ」「発達障害」「ギフテッド」
今や精神科領域だけでなく会社、教育、子供同士の間ですら飛び交う発達に関するこれらのワード。良くも悪くも自分や自身の子がそうなのではないかと気になり、ネットで調べたことのある人もいるかもしれません。ネット上には誰にでも当てはまりそうな特徴や、真偽不明な原因や治療までアクセス数を稼ぐためのサイトが跳梁跋扈しています。
今回は発達障害の中でも「アスペ」などとして話題にされやすい自閉スペクトラム症(ASD)についてその特徴と治療を解説していきます。
目次
・そもそもASDってなんだっけ?
・どんな特徴があるの?8つの特徴
・どういう時に診断されるの?
・どうやって治すの? などなど
ASDと並んで話題にあがりやすいADHDについての解説はこちらの過去記事から↓↓↓
このレターでは、メンタルヘルスの話に興味がある、自分や大切な人が心の問題で悩んでいる、そんな人たちがわかりやすく正しい知識を得ていってもらえるよう、精神科専門医、公認心理師の藤野がゆるくお届けしていきます。是非是非登録して読んでみてください。
そもそもASDってなんだっけ?
ASDは自閉スペクトラム症の略称です。世間ではASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、LD(限局性学習症)などをまとめて発達障害と呼ぶことが多いですが厳密に言うと我々精神科医が用いる診断基準、DSM-5-TRでASDは「神経発達症群」に属します。
神経発達症群は日常生活において様々な障害を引き起こすような発達の問題や脳内プロセスの差異が特徴で、発達期に発症する一群です。知的発達症(知的能力障害)などもここに含まれます。
初っ端から難しい言葉が多くて嫌になりますよね、わかります。定義の話なので最初だけはこんな堅苦しい言葉を使ってみましたが、ここからは平易な言葉で解説していきますので安心してください。
さて、かつてアスペルガー症候群と呼ばれた一群も現在ではASDに含まれることとなっています。そのイメージからかコミュニケーションが苦手という印象ばかり先行しているかもしれませんがASDは
1.社会的コミュニケーションや対人的相互反応における持続的な欠陥
2.限定された反復的な行動、興味、活動
を2本柱とする疾患です。
国や地域にもよりますが有病率はおよそ1%、つまり100人に1人いるとされ、女性より男性に多いことが知られています。
どんな特徴があるの?8つの特徴
ではその「社会的コミュニケーションや対人的相互反応における持続的な欠陥」「限定された反復的な行動、興味、活動」というのは一体どんな形で日常生活に現れるのでしょうか。
ASDの方の困りごととなりやすい特徴を下に8つ挙げたので順に見ていきましょう。
1.他人との距離感を測るのが苦手
まさにコミュニケーションの障害ですね。他人と上手に距離を取ることが苦手で、相手はそんなに仲良くなったつもりはないのに異常な距離の詰め方をしてトラブルになってしまうことがあります。これは決して悪気があるわけではなく、相手の感情を想像することの困難さであったり、言葉を文字通り受け取ってしまう特性から、例えば「また遊びに行きましょうね」という社交辞令を素直に受け取り「次はいつにしますか?」としつこく聞いてしまったりするわけです。また逆に相手がもっと仲良くなりたいということを匂わせてきていても察することが苦手なため気付かず、距離がなかなか縮まらないなんてこともあったりします。
2.興味・感情の共有が苦手
何かを食べて美味しいなと思った時、綺麗な景色を見て感動した時、これを大切な人と味わいたいな、伝えてあげたいなと思ったことはないでしょうか。そういった感情共有をしたいという気持ちやする能力が十分でないと、楽しいことを楽しいと伝えて一緒に楽しむことをしなかったり、相手が気持ちを伝えた際も興味がないように見えてしまうことがあります。
3.非言語的コミュニケーションが苦手
我々は会話をするときに言葉以外のコミュニケーション、身振り手振りであったり表情などを駆使し感情を伝えます。それらの非言語的なコミュニケーションが苦手なため言葉を言葉のみで捉えてしまい、顔をしかめながら伝えた皮肉であっても言外の意味を十分に理解できなかったりします。定時退社をして「ケッ、仕事が早く終わって素晴らしいこった」と言われても褒めてもらえているのだと思い「ありがとうございます」と言えてしまうわけです。