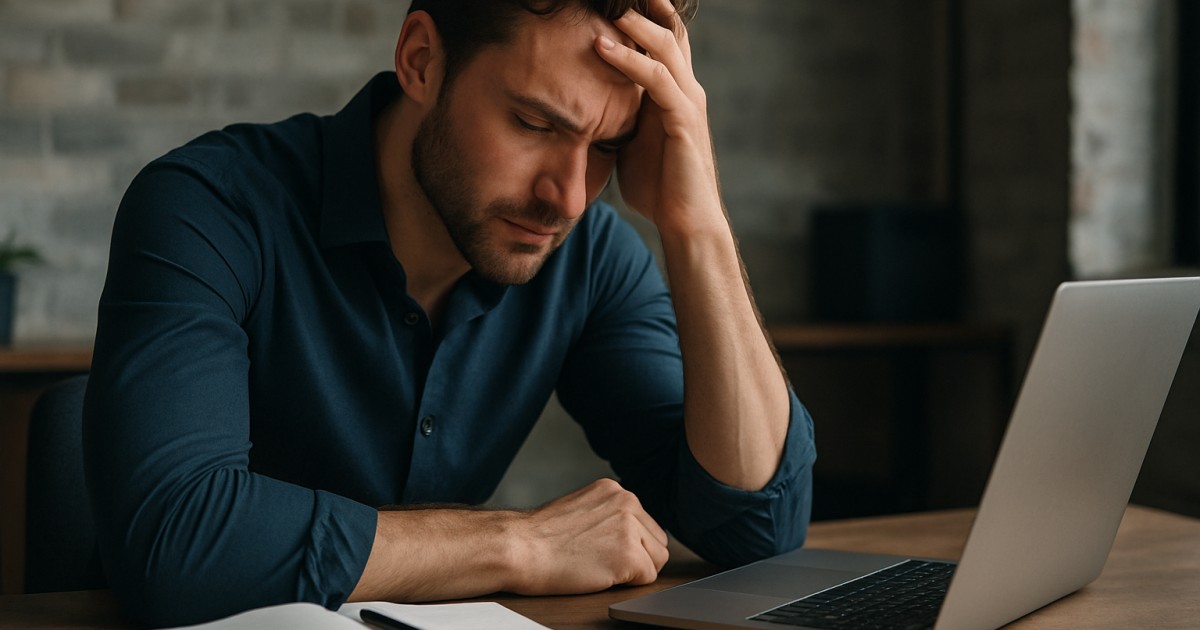ペットロスとの向き合い方、死別に対する正常な悲嘆って?精神科専門医が解説
サポート会員になってくださっている皆様に何か還元できればと開始してみたQ&A企画の解答編、第2弾。
今回は「ペットロスとの向き合い方、死別に対する悲嘆って?」です。
ペットや大切な方との死別を経験した際、しんどくなるのは当然のことですが「早く立ち直らなきゃ」「病気かな」と不安になる人も少なくありません。
中には周囲の人から「いつまでもクヨクヨしていてはいけない」「前を向こう」なんて、良かれと思ったアドバイスを押し付けられしんどくなってしまっている人もいます。
病気と正常な反応の境目は?早く前を向くためにはどうしたらいいのか?そもそも早く前を向く必要があるのか?そんな話をしていきます。
今回寄せられた質問はこちらです。
いつもありがとうございます。
お心のこもったレターを毎回温かい気持ちで拝読しています。
ペットロスへの向き合い方が知りたいです。
個人的な症状のことになってしまい恐縮ですが、最愛の猫を癌で亡くし、心に穴が空いたような気持ちです。
現世における別離の苦しみとどう向き合っていけばいいのか、なにかご助言がありましたらお願いできますと幸いです。
ちなみにQ &Aには結構多くの質問をお寄せいただいたのですが、万人に当てはまる答えのないものや、抽象的なもの特定の薬剤に関するものなどもあったためどれを採用するかなどまだまだ思案中です。
このレターでは、メンタルヘルスの話に興味がある、自分や大切な人が心の問題で悩んでいる、そんな人たちがわかりやすく正しい知識を得ていってもらえるよう、精神科専門医、公認心理師の藤野がゆるくお届けしていきます。是非是非登録して読んでみてください。有料会員になるとこの記事を含め、なんと50本以上の過去記事も全て読み放題になりますのでぜひご検討ください。
悲嘆ってそもそも何?
悲嘆とは愛する人の死によって引き起こされる主観的感情です。
人は大切な人との死別に際し、故人への強い思慕や憧れを持ち、故人への思考や記憶にとらわれ、怒りや悲しみ、苦しさや残された人生を生きることへの虚無感や孤独感に苛まれるものです。
これらは昔から自然なものとして生じ、人々はそういった感情が落ち着くまでの間、喪に服すという文化を形成してきました。しかし、その過程や長さには当然個人差があります。
悲嘆のプロセス
悲嘆は多くの場合、いくつかの段階を経てゆっくりと進行していきます。これには個人差がありますが大きく分けて三つの相があるとされています。
1.衝撃、不信、否認(〜数週間)
大切な人の死にさらされた際に最初に訪れるのが衝撃、不信、否認の相です。
これは大切な人を失った衝撃を受け止められず、信じられず、「まさか」「冗談だろ」と現実を否認し受け入れることに抵抗を示す段階です。
愛しい人との生きての再会を切望し、思慕の情が溢れ、脳内での探索とも言える思考が繰り返されます。これは愛する存在を何とか取り戻したいという強い願望から、姿を探したり、気配を感じたりする心の動きです。
2.鋭い苦痛、虚無(〜数ヶ月)
時間が経つにつれて愛する人の逝去、もう彼とは二度と会えないのだという覆し難い事実を認めるしかなくなり、苦痛の波が押し寄せます。
相手に対する怒りや罪責感、これからの彼なしでの人生に対する絶望、無気力、焦燥など様々な感情が溢れ混乱します。
こういった混乱の最中に、四十九日や相続、さまざまな手続きに翻弄され疲弊してしまう人も少なくありません。
3.再生と再構築、回復へ向けて(数ヶ月〜数年)
これらの辛い辛い時期を経て、最終的には、亡くなった存在は戻らないという現実を少しずつ受け入れ、自分自身の生活や心を再構築する段階へと移っていきます。
この一連の「悲嘆の作業」を経ることで、残された人は亡き存在との関係性を再定義し、心の中で新しくも永続的な絆を結んでいくのです。
予期悲嘆と記念日反応:あらかじめ感じる悲しみもある
また、悲嘆は死別後だけに起こるものだけではありません。