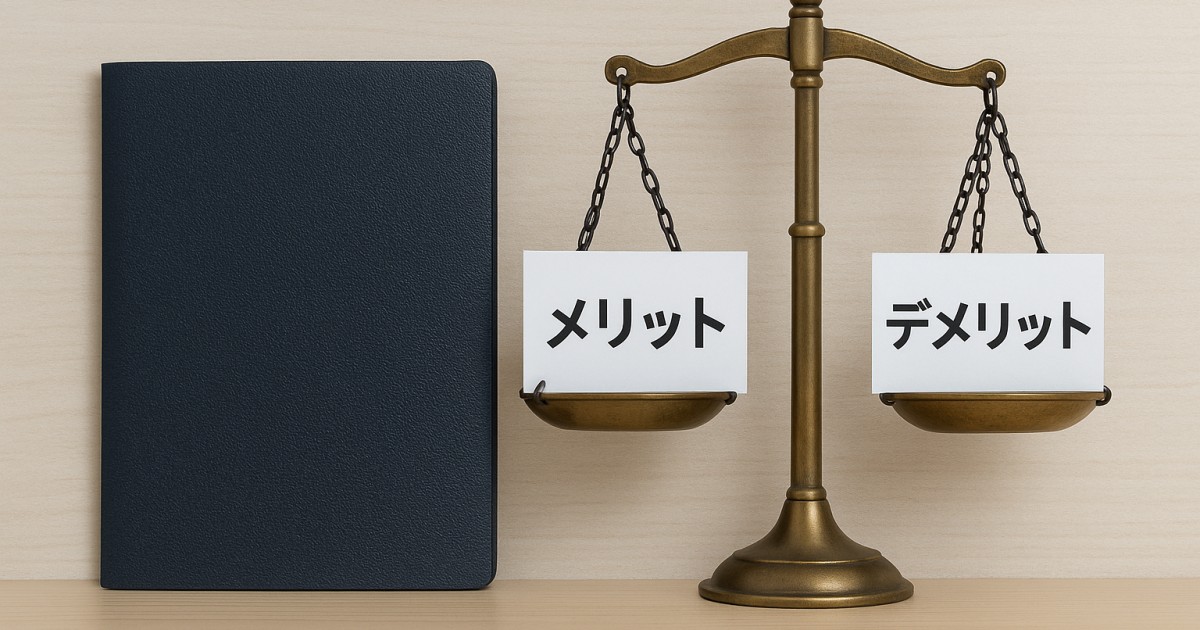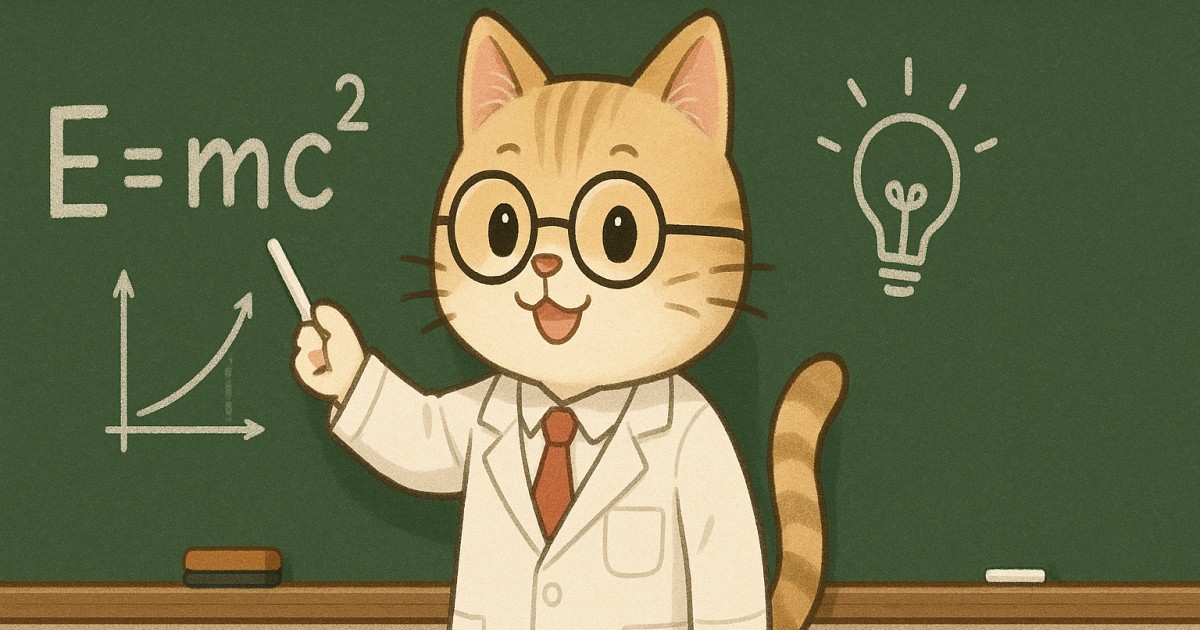ASDと間違えられがち!?社会的コミュニケーション症の特徴4選!精神科専門医が解説
「アスペ」「発達障害」「ADHD」
今や精神科領域だけでなく会社、教育、子供同士の間ですら飛び交う発達に関するこれらのワード。良くも悪くも自分や自身の子がそうなのではないかと気になり、ネットで調べたことのある人もいるかもしれません。
ネット上には誰にでも当てはまりそうな特徴や、真偽不明な原因や治療までアクセス数を稼ぐためのサイトが跳梁跋扈しています。
またASDやADHDなどは特によく知られており、専門外の医師でもそれらしく病名をつけることがありますが、ASDと症状が重なる部分の少なくない社会的コミュニケーション症(Social Communication Disorder)については残念ながら知らないという医師も少なくありません。
今回はASDでもみられることのある「語用論」の障害と社会的コミュニケーション症という疾患の特徴、ASDとの違いなどについて解説していきます。
聞きなれない言葉ばかりで嫌になりそう、なんて人に向けて言葉の解説からしていきますので安心して読んでくださいね。
また、そもそもASDってという方はこちらの過去記事もご覧ください。
このレターでは、メンタルヘルスの話に興味がある、自分や大切な人が心の問題で悩んでいる、そんな人たちがわかりやすく正しい知識を得ていってもらえるよう、精神科専門医、公認心理師の藤野がゆるくお届けしていきます。是非是非登録して読んでみてください。
そもそも語用論って何?
そもそも「語用論」なんて言葉聞いたことないよ、やっぱり専門的な話を理解するのは無理だよ。
なんて思った人がほとんどでしょう。
でも大丈夫、そう難しい話ではありません。
語用論というのは「社会的、対人的な文脈において適切な方法で言語などを用いて言語を理解する能力」のことです。
まだ難しいですよね、もっと噛み砕きましょう。
我々は普段、状況に応じて言語的、非言語的な方法を用いて互いに自然なコミュニケーションを行っています。語気を強めて怒っていることを伝えたり、逆に怒っている人には穏やかなトーンの声で傾聴しようとしている気持ちを伝えて怒りを鎮めようとしたりもするでしょう。
このように半ば無意識、自然に行われている、相手の状況や社会的な状況に合わせてコミュニケーションをとるための理解能力が語用論の根幹です。
まさにその語用論のその困難さ、障害を抱えるのが社会的コミュニケーション症なのですが具体的な話がないとわかりにくいですよね、症状を例を挙げながら見ていきましょう。
社会的コミュニケーション症って?
社会的コミュニケーション症は我々精神科医が用いる診断基準、DSM-5-TRでは「神経発達症群」に属します。
神経発達症群は日常生活において様々な障害を引き起こすような発達の問題や脳内プロセスの差異が特徴で、発達期に発症する一群です。
ASDやADHDなど、世間でいわゆる「発達障害」とされている疾患や知的発達症(知的能力障害)などもここに含まれます。
その神経発達症群の中でも言語、会話、コミュニケーションの欠陥という特徴を持つのがコミュニケーション症群と分類される一群で、さらにその中で先ほど言った語用論の障害を抱えているのが社会的コミュニケーション症です。
ま〜た難しい話が始まった、と思いましたよね。
ここからはわかりやすい具体例を挙げて話をしていくので大丈夫です、トントンいきましょう。
社会的コミュニケーションの特徴
1.挨拶や情報共有といった社会的目的でコミュニケーションを用いることの欠落
我々は社会で生活する中で、それ自体に意味のない言葉であってもキャッチボールをすることがあります。
例えば挨拶という行為はそれ自体がお金を生み出さない、会社での業務内容には含まれていないものではありますが、半ば暗黙の了解のように職場で会った人とはあいさつをします。
また、久々に取引先の相手に会ったとして、会った瞬間から契約の話はせず「最近どう?」なんて互いの情報を共有するところから始まりますし、それをすることで深まる仲もあるでしょう。
親子間でも、深い意味はなくても「今日こんなことがあった、こんな気持ちになった」という話を共有してわかり合いたい、気持ちを抱え合うのが自然でしょ?と思うかもしれません。
しかしこの疾患の患者さんはそもそもの特性としてそういったことが困難なわけです。