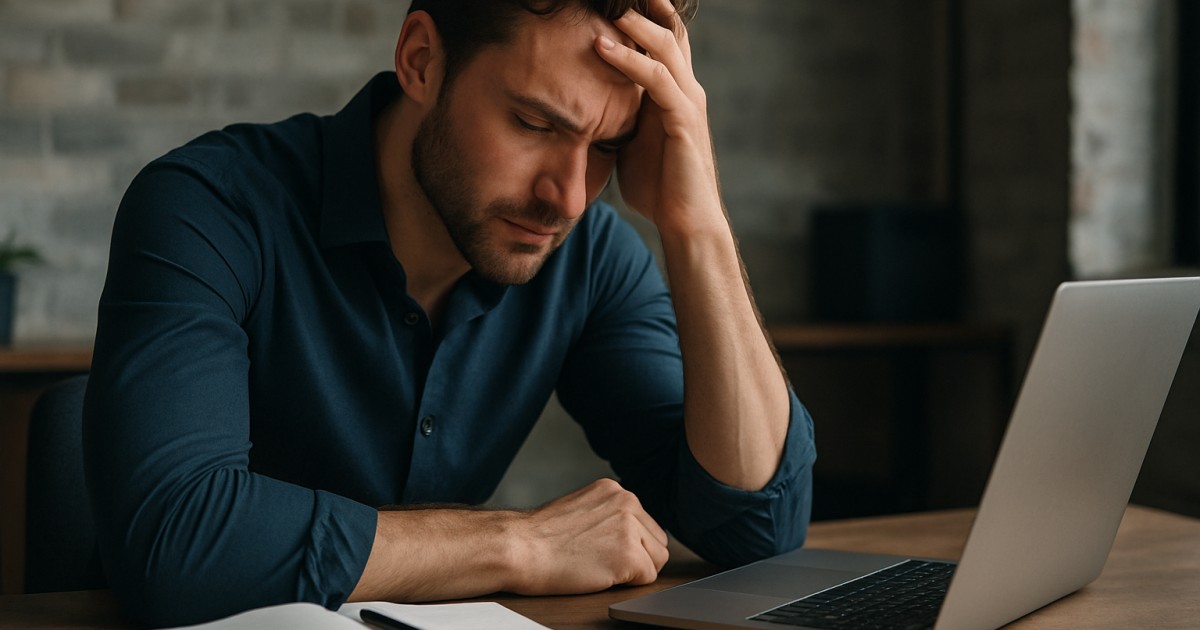相次ぐ高齢者の自動車事故と認知症の現実
10月15日朝、名古屋駅前にて71歳男性の運転する車が横断歩道に突っ込み3人の死傷者を出す凄惨な事故を引き起こしました。
2019年には池袋の乗用車暴走事故では当時87歳だった男性の運転により計11人の死傷者が出て世間の注目を集め、その年は運転免許証の自主返納数が跳ね上がったもののその後は右肩下がりとなり、ブレーキとアクセルの踏み間違いによりコンビニへ突っ込む、児童の列に突っ込むなど高齢者による自動車事故が社会問題として繰り返し報道されています。
そんな現状を踏まえ、徐々に道路交通法の改正なども進んできてはいますがまだまだ充分とは言えません。
また、こういった事故が起きると「免許の返納」について声高に叫ぶ専門家もいますが、実際に認知症の方やその家族を臨床の現場で見ているとその効果は限定的だと感じざるを得ない部分もあります。
今日は高齢者の免許制度、そして返納や認知症との関わり、その現実について認知症疾患医療センターの副院長も務める精神科専門医が解説していきます。
このレターでは、メンタルヘルスの話に興味がある、自分や大切な人が心の問題で悩んでいる、そんな人たちがわかりやすく正しい知識を得ていってもらえるよう、精神科専門医、公認心理師の藤野がゆるくお届けしていきます。腰が痛い中ヒーヒー言いながら必死に書いています。是非是非登録して読んでみてください。有料登録をすると無料記事に加えて毎月2本の有料記事、そしてなんと数十本の過去記事も全て読み放題になります。
そもそも高齢者って?
「高齢者」という言葉の定義は国や時代によって移り変わるものですが、現在、世界保健機関(WHO)では65歳以上を高齢者としています。
日本でも医療制度において65歳から74歳までの「前期高齢者」と、75歳以上の「後期高齢者」と分けられたことが記憶に新しいかと思います。
ただ日本では「高齢者」の定義が行政上の目的や制度によっても異なることが少なくなく「改正道路交通法」では70歳以上を高齢者とし、高齢者講習をはじめとした様々な検査を導入しています。
高齢者講習と認知機能検査の流れ
70歳以上のドライバーが免許を更新する際には、「高齢者講習」を受ける必要があります。ここでは運転適性や動作能力、交通ルール理解度などを確認します。
さらに、更新時点で75歳以上かつ過去3年以内に一定の違反がある場合は、「運転技能検査」も義務化されました。これに不合格となると免許更新はできません。
また、75歳以上では認知機能検査も全員が対象です。
こう聞くと国もしっかり対策をしているんだな、安心だなと思う人もいるかもしれませんが、実際はとても充分とは言えない対策です。だからこそ現に凄惨な事故が日々繰り返されています。
一体これらの対策の何が問題なのでしょうか、精神科医の目線から見ていきましょう。
高齢者講習
まず、高齢者講習についてです。高齢者講習では2時間をかけ運転の適性検査や講義、技能検査を受けない方には実車試験が行われます。これに関しては全く意味がないとは言いませんが、これを読んでいるみなさんの中にも免許を更新する際の講習や違反者講習などで「あまり意味がないな」と思いながら数十分の講義を聞き流したことがある人もいるのではないかと思います。
結局真面目に聞く人にとっては役立つ内容であっても、縛りのない講義などでは結局必要な人間ほど聞かないという現象が起こるため十分な効果が出ないことが多々あります。
再受験可能な運転技能検査
そして問題はここからです。
運転技能検査に関しては、実際に普通自動車を用いてコース等を走行して一時停止ができるか、信号を守れるかなどの基本的な運転技能について減点方式で採点されます。
これ自体は素晴らしいことですがここには大きな問題があります。それは期間内であれば何度でも再受験できることです。
能力がなくて試験に落ちているのに、再受験ができてしまう。意味がわかりません。
その日のコンディションがたまたま悪く落ちてしまった人のため、という立て付けなのかもしれませんが、その人はコンディションが悪い日に運転したら自動車事故を起こす可能性があるから検査に引っかかったわけです。それがコンディションの良い日に合わせて免許を与えるために何度も受験をさせるということが適切でしょうか。
そもそも同じような試験内容であれば何度も受ければ学習効果が出てきますから、その試験においては結果が上がります。しかし、実際の運転では当然同じコースばかりを走るわけではありません。