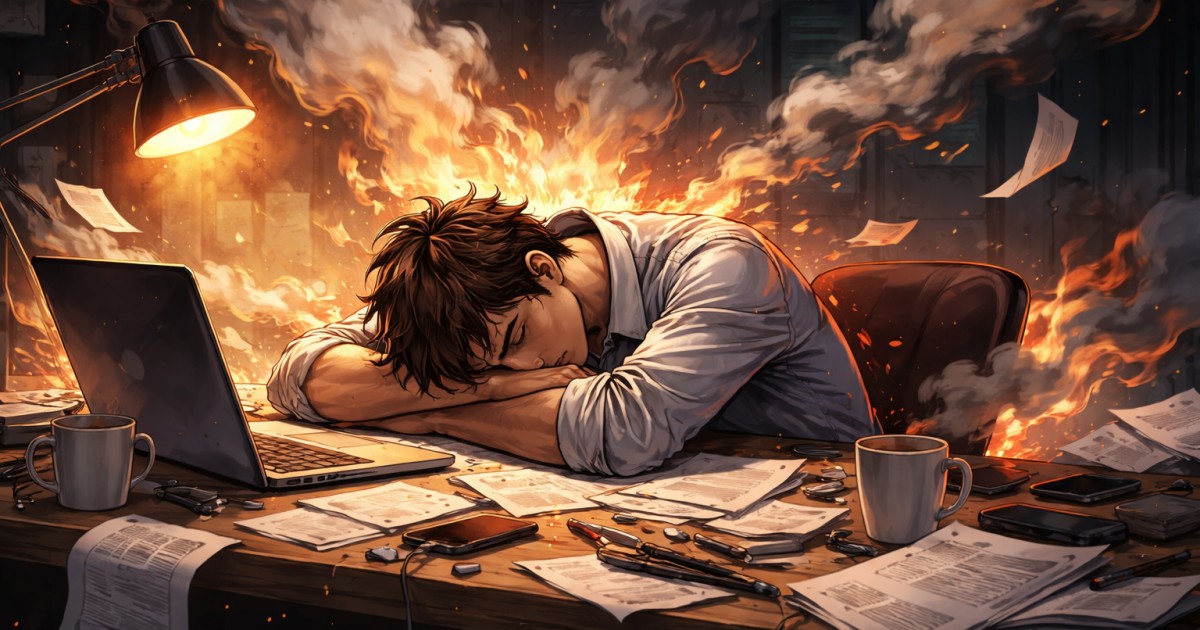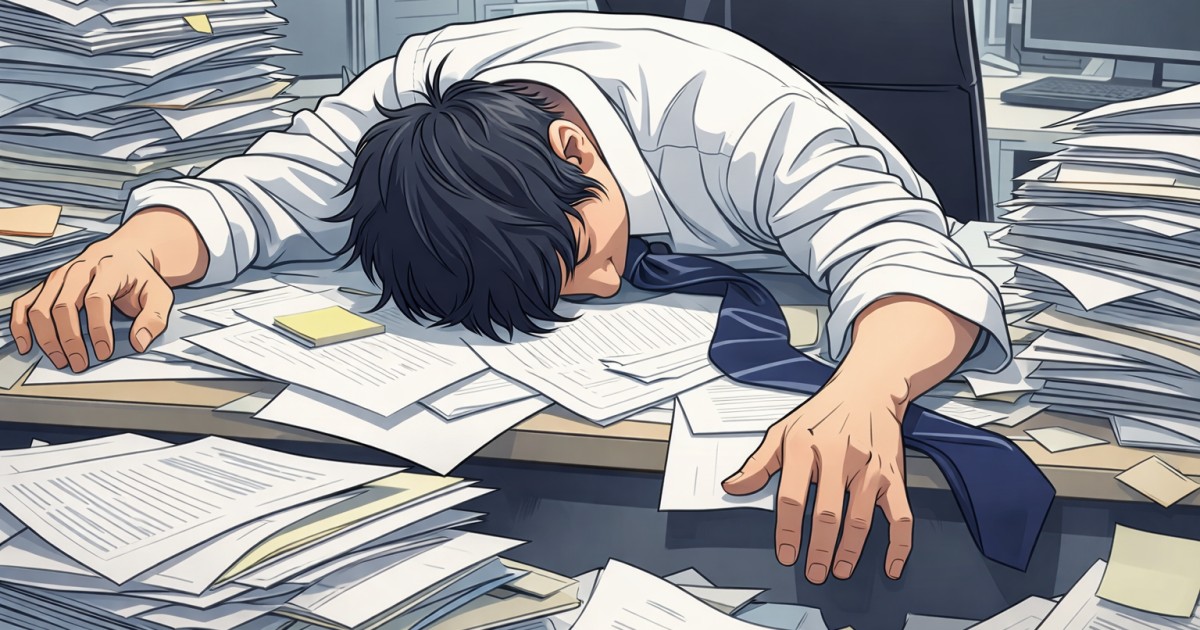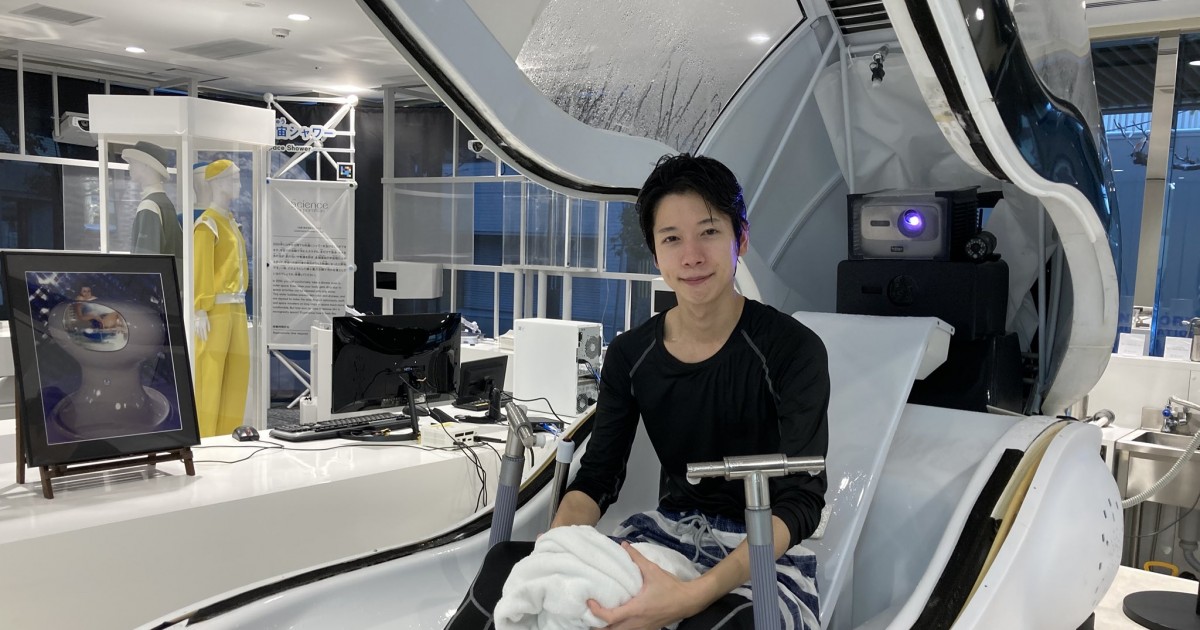ADHDだと生活にどんな問題が出るのか?薬物治療以外でできること 精神科医が徹底解説
ADHD(注意欠如多動症)という病名が広く知られるようになり、ネットを見れば病気についての知識は多く得られるようになりましたが、難しく書かれていたり玉石混合で何が正しいのかよくわからないという方も少なくないでしょう。
今回はADHDの特性を持った方の実生活の中で出てきやすい症状とその対策を解説していきます。自身だけではなくお子さんや同僚などの症状がなぜ起こるのか、どう関わったらいいのかわからない、なんて人にもおすすめです。
このレターでは、メンタルヘルスの話に興味がある、自分や大切な人が心の問題で悩んでいる、そんな人たちがわかりやすく正しい知識を得ていってもらえるよう、精神科専門医、公認心理師の藤野がゆるくお届けしていきます。是非是非登録して読んでみてください。
ADHDってそもそも何?
ADHD(attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)は注意欠如多動症と訳され、その名の通り多動、不注意、そしてそれに加えて衝動性が大きな特徴とされる疾患です。男性に多く、成人でもおよそ2.5%がADHDだというデータもあります。100人の会社なら2、3人、数千人規模の会社なら数十人はいる計算です。
「発達障害」という言葉ばかり先走り一人歩きしがちですが、厳密に言うと我々精神科医が用いる診断基準、DSM-5-TRでADHDは「神経発達症群」に属します。
神経発達症群は日常生活において様々な障害を引き起こすような発達の問題や脳内プロセスの差異が特徴で、発達期に発症する一群です。知的発達症(知的能力障害)や自閉スペクトラム症もここに含まれます。
いきなり難しい言葉や分類の話が始まってもう嫌になっている人も多いと思いますのでここからはわかりやすい症状について見ていきましょう。
なお、ADHDの不注意や多動衝動性がどんなものなのかなどは過去記事でも解説しているのでそちらもご覧ください。