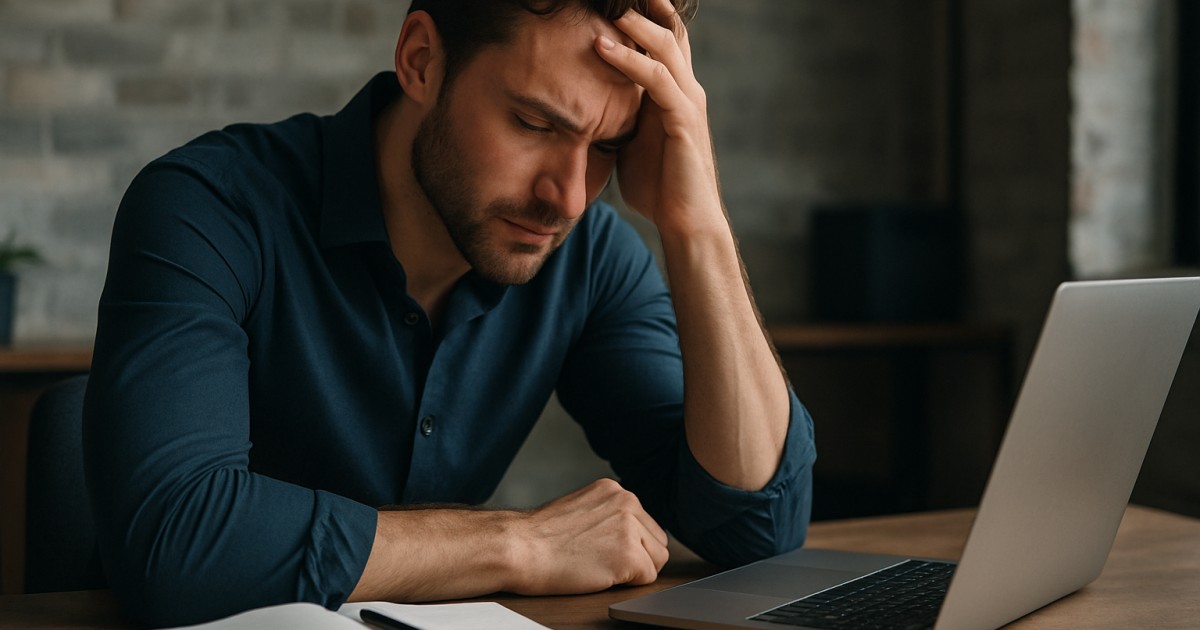〜薬を使わない不眠症治療〜睡眠スケジュール法って?精神科専門医が解説
「寝つきが悪い」「夜中に何度も起きてしまう」「目覚ましがなる前に目が覚める」
そんな悩みを抱える人にとって、睡眠はもはや休息ではなく苦痛になっているかもしれません。
夜が近づくにつれ「また眠れなかったらどうしよう」と考えますます寝られなくなる、そんな人も少なくないでしょう。
現在では依存性や副作用などの少ない薬も出てきてはいて、それらを上手に使う分には薬も悪くないというのが私の個人的な考えですが、薬を使うことに抵抗がある人の気持ちもわかります。
そういった人のため、欧米では治療の第一選択として推奨もされる不眠症に対する認知行動療法(CBT-I)、その中でも中核的技法である睡眠スケジュール法について解説していきます。
このレターでは、メンタルヘルスの話に興味がある、自分や大切な人が心の問題で悩んでいる、そんな人たちがわかりやすく正しい知識を得ていってもらえるよう、精神科専門医、公認心理師の藤野がゆるくお届けしていきます。腰が痛い中ヒーヒー言いながら必死に書いています。是非是非登録して読んでみてください。
睡眠スケジュール法」って?
不眠症に対する認知行動療法は、欧米では第一選択治療とされており、中でも「睡眠スケジュール法(sleep scheduling)」は、全4〜8回程度のセッションという比較的短期間で変化が得られやすいアプローチとして注目されています。
この方法は、眠れない原因を「寝床=睡眠」という条件が崩れてしまっていることや睡眠リズムの乱れに見出し、睡眠と覚醒のリズムを再構築していく手法です。
つまり、「長く布団にいれば休まる」という直感とは逆の発想で、「眠れる時間帯を見極め、そこに合わせてスケジュールを組む」ことが基本になります。
どうやって行うの?
もちろん治療として認知行動療法を行う際は専門家が状態を確認してフィードバックなどをしながら施行していくものですが今回は概要とその考え方について説明していきます。
では、具体的にどのように進めるのか。以下①〜⑤が基本ステップです。
① 過去1週間の平均睡眠時間を把握する
まずは、睡眠日誌などを使って自分が実際に眠れていた時間を把握します。たとえば、布団に7時間いたけれど実際に寝ていたのは5時間なら、「平均睡眠時間は5時間」と考えます。
② 臥床時間を「平均睡眠時間+30分」に設定
次に、布団の中にいる時間を実際の睡眠時間+30分に設定します。上の例なら5.5時間です。
ただし、5時間以下にはしないことが基本ルールなので、例えば睡眠時間が平均4時間の場合でも5時間とします。
③起床時間、就床時間を決定する
決まった臥床時間に合わせて、起きる時間と寝る時間を決めます。
例えば上の例だと5.5時間になるので、何時に起きるかを決め、そこから逆算して寝る時間を決めてみましょう。
まぁ、どうせ6時には目が覚めるから、、夜は0時半に寝ることにするか、といった感じです。