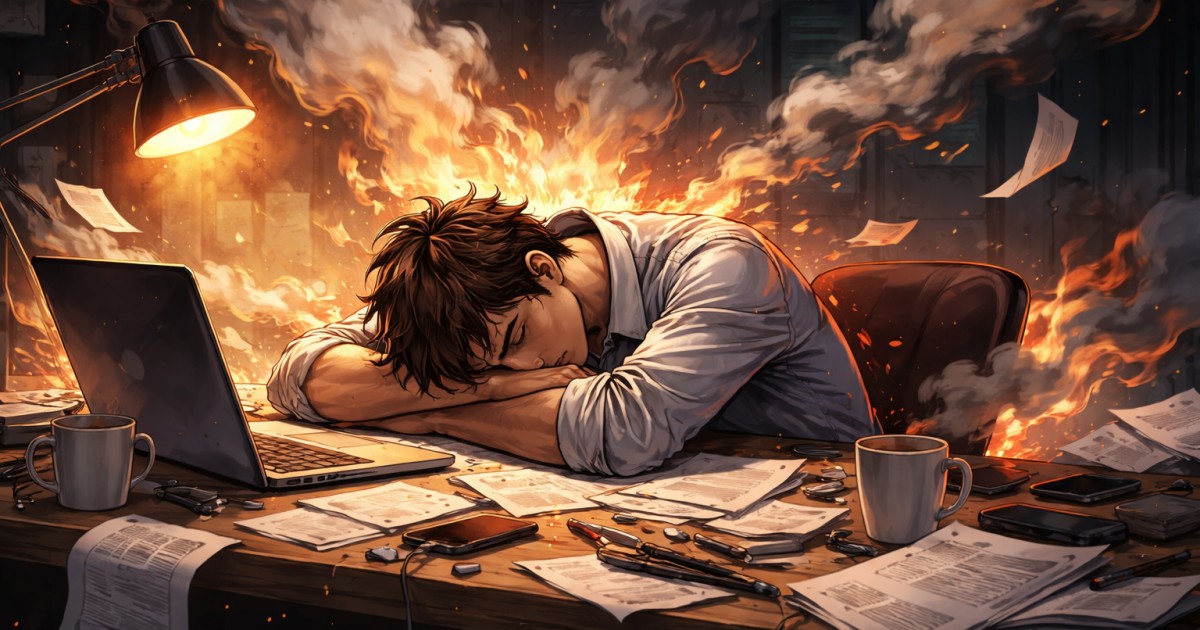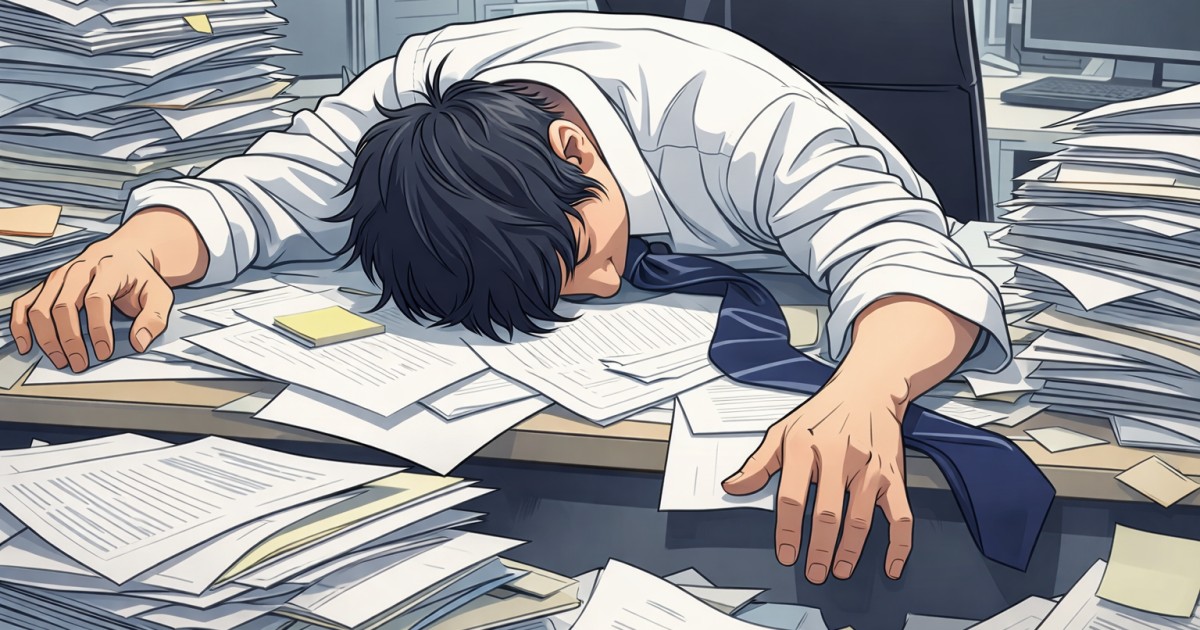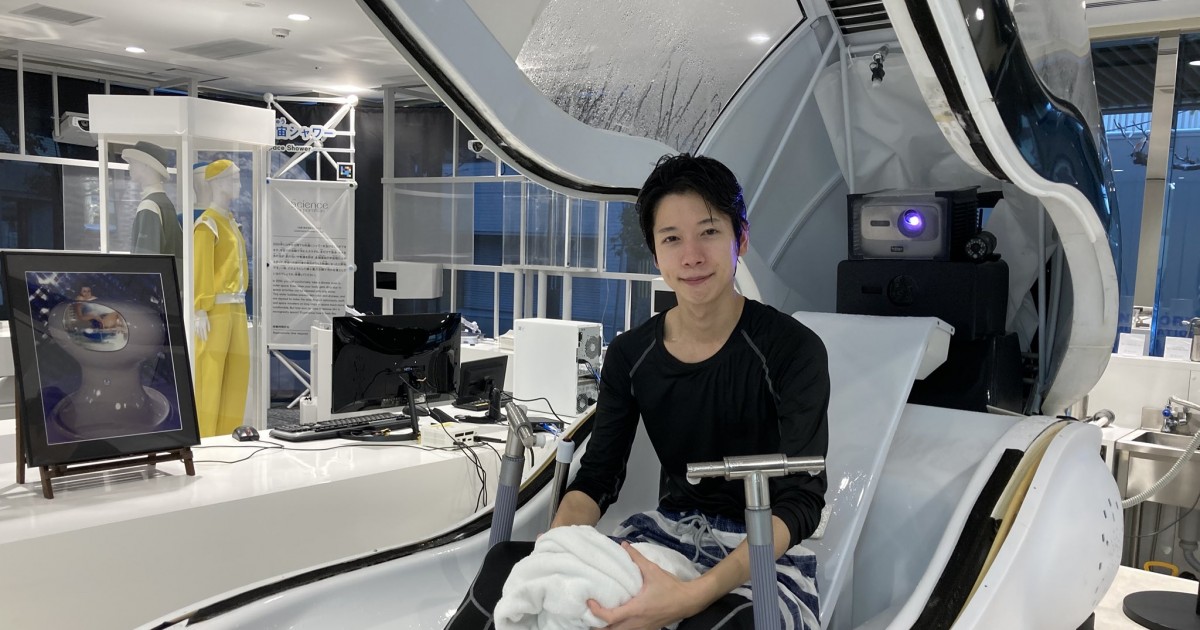精神科には甘えの患者もくる!?うつ病の拡大に精神科専門医が警鐘
この大ストレス社会において自身や身の回りの人が精神疾患になることは珍しくなく、精神科の話は決して他人事ではなくなりました。一昔前までは「精神疾患なんて甘えだ」「気の持ちようだ」と言っていた勢力も徐々に衰退し始めているのではないかと感じることもあります。
ただ、私が今日始めにはっきり述べておきたいのは精神科の病気が甘えではないということと、精神科にくる人が全員甘えではないということは別の話だということです。
これは非常にセンシティブな話題であり、文章だけで充分伝えられるか難しいところだと思っていたのでこれまでどこにも書かずにきたのですが、ここをはっきりさせておかねば多くの実際に苦しむ患者さんにも不利益となりますし、それを利用して金儲けを画策している企業によって今後様々な問題が生じることになるのが目に見えているため今回問題提起として書くことにしました。
精神科に来る人の中には甘えや、甘えどころかそもそも利得を得るために来る人が確実に存在します。私がいつも述べているように精神科の病気自体は甘えでなるものではありません。内因性の疾患、例えば「うつ病」などは脳の疾患であり、遺伝素因を始め様々な生物学的な要素加え生活史的な要素が関わり発症すると言われています。
しかし、病気でなくても受診することはできます。ここで注意して欲しいのは病気でないのに病院に受診することが全て悪いといっているわけでもありません。病気かどうか判断がつかず心配で受診こと自体は全く問題はありません。受診した結果、病気でないとわかり安心できればそれが一番ですから。
問題は病気でないのに、病気になろうとする人です。本来ならばそんなことは起こり得ないのですが様々な利得から、病気になろうとして病院に来る人がいて残念ながら現代の精神科ではそれがまかり通ってしまう可能性があります。
なぜそんなことが起こるのか、操作的診断基準が跳梁跋扈している時代にあまり「昔はこうだった」と老害のような話をしても仕方ないのでそこは少し触れる程度にしつつ、精神科の診断と制度が正しく用いられなければ今後の日本を滅ぼす可能性があるということを話していきたいと思います。
このレターでは、メンタルヘルスの話に興味がある、自分や大切な人が心の問題で悩んでいる、そんな人たちがわかりやすく正しい知識を得ていってもらえるよう、精神科専門医、公認心理師の藤野がゆるくお届けしていきます。寒くなってきて腰が痛い中ヒーヒー言いながら必死に書いています。是非是非登録して読んでみてください。
精神科における診断
この話をするにあたり、まずは皆さんに精神科における診断というものについて知ってもらう必要があります。といっても当然個別の病気の診断基準を知って欲しいわけではありません。
私が疾患を説明する時によく話に出す診断基準、DSMやICDと呼ばれるものの問題点に関しては下記の記事でも触れていますのでそれはまたそちらをじっくり読んでいただければと思いますが、それもめんどくさい人のために一部抜粋します。
採血や画像など客観的にみても根拠が明確に示される他科の疾患と異なり、精神科の疾患の多くは目に見えません。そのため根拠に基づいた診断や治療を行うため近年、精神疾患の診断においてはICDやDSMという国際的な診断基準が用いられています。診断基準に当てはめることで誰でもどこでも根拠のある画一的な診断ができるようになる。一見素晴らしいことのようですが、その時の状況だけをみて当てはめるだけであればサルでもAIでもできます。そうして機械的に当てはめた結果、人間の心の動きを考えれば自然な反応と思われるものまで「病気」と過剰診断されてしまう可能性が出てきます。そこで我々精神科医の診察が重要になるわけですが、そこにはどうしても医師個人の考えが介入してしまうためそれはそれで医師によって診断が異なる、という新たな問題が出てきます。チェーンのクリニックなどで非精神科医がバイトをしているところなどでは画一的に診断基準に当てはめマニュアル通りの薬を出すため「うつ病」患者が量産される一方、寿司職人のように独自の考えを盛り込んで診療するベテラン医師は独特な意見で病気の人を見逃す可能性もあるわけで、一長一短ある状態です。回転寿司と職人の握る寿司、それぞれに良さがあり悪さがあるようなものだと思っていただければ良いかと思います。
こんな状況ではありますが、現在の精神科診療においては診断基準を遵守して診断していくことが求められており、それに関しては上述のように良い点もあります。
ただ、私はもしかするともはや老害となりつつあるのかもしれませんが、この診断基準に画一的に当てはめる診断の仕方には大きな危惧を覚えています。ここから派生して起こってきているうつ病概念の拡大、そして社会の崩壊についてお話をしていきます。
外因性、内因性、心因性という考え方
本来、精神科医をやる上で避けては通れない考え方に外因性、内因性、心因性という考え方があります。皆さんはそこまで詳しく知る必要はありませんが、この概念が今回の話と少し関わってきますので、軽くだけ説明しておきます。ここが十分にわからなくても今後の話はわかるので心配しなくて大丈夫です。
【外因性】
外因性の精神疾患とはその名の通り外部からの影響で脳が破壊される、機能不全が出るなどの状態となって症状が現れているものを指します。例えば頭部外傷、脳卒中、脳炎、ホルモンの異常や薬物などにより脳の構造の破壊や機能不全が起こり、幻覚や妄想などが出ているケースが当てはまります。精神疾患を疑われ受診した人が実は脳炎や違法薬物による症状であることは少なくなく、外因の除外は精神科の診療において真っ先に行われるべきことです。そのため精神科に受診したのに採血や画像検査が行われたり、他科へ紹介をされることがあるわけです。
【内因性】
それに対し、内因性の精神疾患では外からの影響からある程度独立して自律的に障害が生じます。ここには遺伝的な素因や生活史的積み重ねなどが影響し、ある程度までは可逆性、可塑性を持つと考えられています。生活史上の特定の出来事がその発症において大きな影響を持つことはありますが、だからといってその出来事が解消されても適切な投薬や休息が得られなければ病態は一定程度まで進行、悪化します。難しい言葉ばかりで嫌になりましたよね?わかりやすく例を上げましょう。
例えばうつ病。とてもひどい上司がいて、パワハラを受けうつ病が発症したとします。食事は取れず、眠れない。意欲の低下、抑うつ、自分はとんでもないことをしてしまった、取り返しがつかないという絶望。それらに支配され生じてくる希死念慮。
これはこの上司がある日クビになりいなくなったとしても、当然翌日にスパッと良くなるものではなく、きっちりとした治療が一定期間必要になることが想像できるかと思います。
【心因性】心因性の疾患は皆さんも一番イメージがしやすいものかもしれません。何か外的なストレスに対して反応的にしんどくなり症状が出る、そしてそのストレスが消失すれば自然と症状は軽快していくような物を指します。その人の生活史を見たときに、その人のその状況であればそういった気持ちになりそういった症状をきたすだろうなと理解が可能な物です。例えば前日、同僚に陰口を言われていたことがわかり言い合いになってしまった。その日は眠れず、翌日も会社に行こうと思ったらお腹が痛くなってきた。これは脳に問題が生じていなくても十分に起こり得ることとして理解が可能ですし、同僚と仲直りができればもしかしたらその日のうちに症状は良くなるかもしれません。
うつ病概念の拡大
さて、例にも挙げたように元来、我々精神科医が用いる「うつ病」という言葉は内因性の疾患でした。「嫌なことがあってしんどくなった、その原因さえなくなれば勝手にすっきり良くなる」というような単純な心の反応ではないからこそ、「気の持ちようではない」「脳の病気である」と言われてきたわけです。そのため中等症以上になれば心理療法だけで済ませるのではなく薬物治療なども積極的に行われます。
しかし、現代で精神科が用いる診断基準には内因、心因という概念や区別は記載されていません。最初に述べたようにその時の症状をピックアップし当てはめていくことで診断をするシステムになっています。これにより、うつ病概念の拡大が起こりました。
本来の内因性の疾患でなくとも、例えば辛いことがあり、自然な範囲の反応であろうとされてきた反応性の抑うつであっても場合によっては基準に当てはまれば「うつ病」と診断されることが増えて来たのです。
誰でもどこでも扱うことができ、画一的な診断を受けられるように、という理念のもと作られた診断基準ですから、非専門の医師でもこれを用いれば「うつ病」という診断ができます。例えそれが人間として自然な反応であっても、何も考えずにその瞬間を切り取り当てはめ、当てはまっていればうつ病になってしまいます。もっと言えば、病気になりたくて診断基準を見て準備をして来た人がその症状を読みあげれば、不慣れな医師によりうつ病にされてしまいかねないわけです。
製薬会社と疾患概念の流行
うつ病が流行ってきたことには他にも理由があります。流行り、という言葉に驚いた方もいるかもしれませんが、残念なことに実は精神科の病気にも流行り廃りがあります。これは製薬会社が営利企業であり薬を売って成り立っている以上、仕方のないことですが薬が開発された病気は流行ります。といっても風邪のように人から人へうつり、流行していくという意味ではありません。