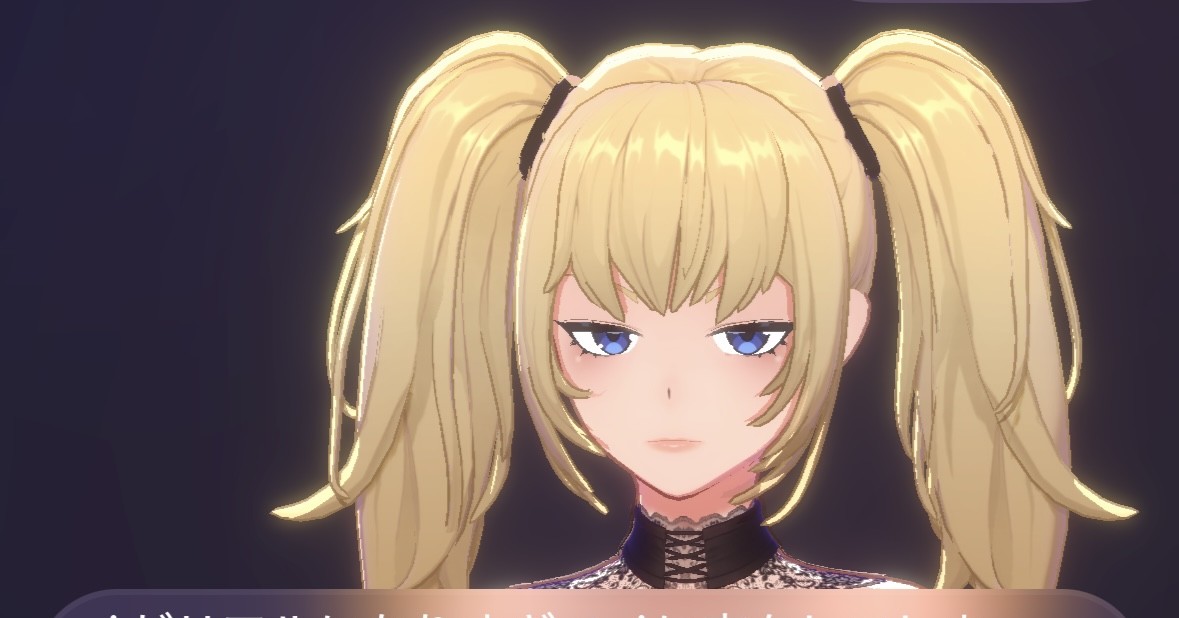【愛着の話は大嘘ばかり!?】愛着障害の真実を精神科専門医が解説
「発達障害の原因は愛着障害」「愛情不足にも問題がある」
そんな話を聞いたことがあるかもしれません。愛着、アタッチメントなどの言葉は臨床家と研究者、そして発達心理学、社会心理学などでそれぞれ異なる使い方をされ、定義が曖昧になってしまっている部分もあります。
ネットを見ると自分で「愛着障害」と自己診断している人も多くいますが、我々精神科医が診断する機会は実はそう多くありません。ただ残念なことに診断がつかない時に「愛着の影響もあるかもね」なんて言葉を便利使いする医師もいて、患者さんはそれを愛着障害と勘違いしていることもありますし、診断されてなくても自分でそういうことにしてしまっている人もいます。
愛着という言葉が便利に大安売りされた結果むしろあまり知られなくなった、我々精神科医の診断する愛着障害というものについて解説していきます。
このレターでは、メンタルヘルスの話に興味がある、自分や大切な人が心の問題で悩んでいる、そんな人たちがわかりやすく正しい知識を得ていってもらえるよう、精神科専門医、公認心理師の藤野がゆるくお届けしていきます。寒くなってきて腰が痛い中ヒーヒー言いながら必死に書いています。是非是非登録して読んでみてください。
そもそも愛着って?
愛着(アタッチメント)に関する理論はそもそもイギリスの精神科医ボウルビィによって広く知られるようになりました。彼は小さい子供と養育者の関係のあり方に着目をし、愛着を人間という生物の適応行動であると捉えました。つまり、養育者に接近をした乳幼児はポジティブな応答が得られればその行動を維持し、それに対して養育者は栄養や保護を与える。相互的に成り立ち深まっていく生物としての仕組みです。また、乳幼児は通常養育者に通常愛着を形成し、その愛着関係の安定さ、不安定さによりその後の自己と他者の関係が規定されると考えました。つまり、愛着がその後の人生にも影響してくると考えたわけです。
一方、アメリカの発達心理学者エインズワースは愛着を「時間や空間を超え人と人を結びつける継続的で情緒的なもの」と考えました。日々の困難に立ち向かう際の安心感の源やストレスや危険のある状況での安全な避難所の役目を果たし感情の調整を助けるのが愛着の相手となる愛着対象(養育者など)であると考えたのです。日々の辛い出来事も愛着の対象となる相手がいるから乗り切れる、もしかしたらこちらの方がみなさんが考える「愛着」というもののイメージと近いかもしれません。彼女はストレンジシチュエーション法という方法で愛着の安定性を測定することも提唱しましたがそれに関してはまたの機会に。
ここで重要なことは不安定な愛着が必ずしも愛着障害と直結しないことです。不安定な愛着であってもその愛着関係から児童は心理的な資源を得ることはあり、欠損しているわけではないのです。
さて、愛着というものの定義自体も多少なりその研究者や時代によって異なっているため軽い気持ちで用いられる「愛着障害」という言葉がいかに当てにならないかがもうわかってきたかもしれません。
では我々精神科医が「愛着障害」を診断するときそれは一体どういうものなのか見ていきましょう。